この記事で解決できるお悩み
- 産後の鉄分不足の影響が知りたい
- 産後に摂るべき鉄分豊富な食べ物が知りたい
- 効率のいい鉄分の摂取方法が知りたい
産後のママにとって、鉄分補給は体調回復の重要なカギとなります。
 Yuri
Yuri出産による出血や授乳によって鉄分が失われるため、適切な補給が必要です。
以下、鉄分の推奨量です。
| 月経が再開する前の 場合 | 8.5~9mgを 推奨 |
| 月経が再開した 場合 | 10.5~13mgを 推奨 |
記事前半では産後の鉄分不足の原因や体調変化について、後半では鉄分が豊富で摂りやすい食べ物をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
体調不良に悩むママが健やかな日々を取り戻すための情報をお届けします。
この記事を参考にして、積極的に鉄分を補給しましょう。
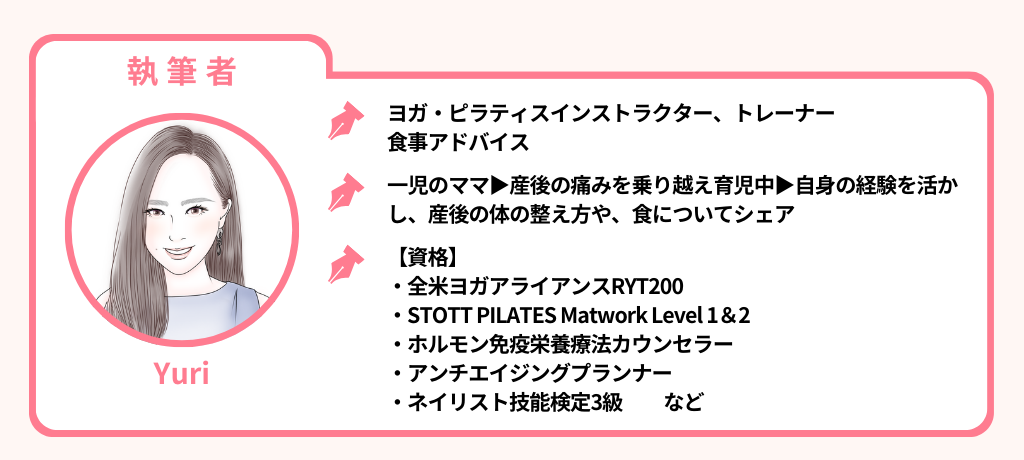
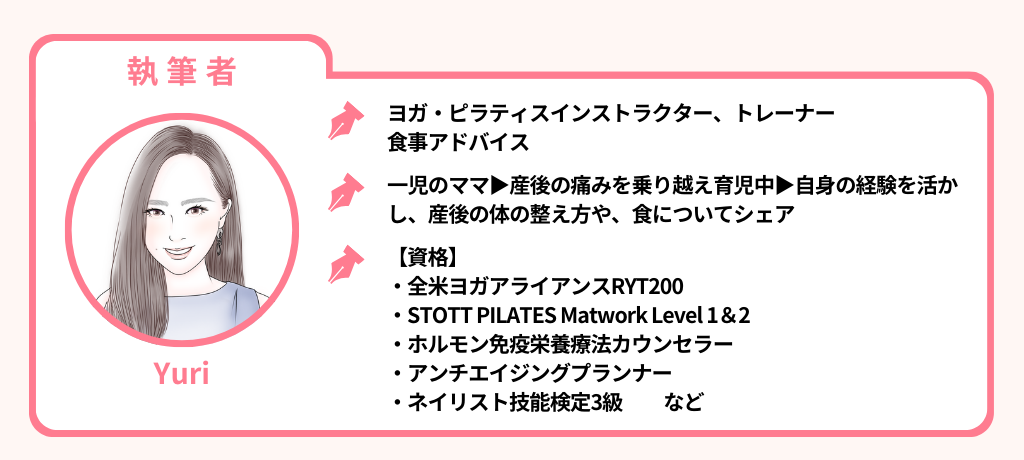
産後の鉄分不足の主な原因とは?


産後に鉄分が不足する主な理由は、出産時の出血と授乳です。
自然分娩では300ml以上、帝王切開ではさらに多くの血液が失われ、体内の鉄分が減少します。
また、育児による睡眠不足や不規則な食事も鉄分不足を招く要因です。



育児の忙しさから食事の時間や内容が十分でなくなり、鉄分の摂取量が減少しがちです。
これらの要因が重なり、多くのママが産後に鉄分不足になりやすいと考えられています。
特に妊娠前から鉄分が不足していた場合は、産後の回復が遅れることもあるのです。
そのため、産後には適切な対策が必要です。
産後の鉄分不足による体調変化とリスク


産後に鉄分不足になると、さまざまな体調の変化が現れやすくなります。
以下では、鉄分不足がもたらす影響について解説します。
体調の変化
鉄分が不足すると、疲れやすさやだるさを感じやすくなります。
これは体中に酸素を運ぶヘモグロビンの主成分が鉄分であるため、不足すると体中に十分な酸素が届かなくなるからです。
また、集中力が続かなかったり、物忘れしやすくなることも。



これは「ママ脳」と呼ばれる現象の一因にもなっています。
さらに、めまいや立ちくらみ、頭痛や肌の乾燥、爪が割れやすくなったり、髪の毛が抜けやすくなるといった変化が起こることもあります。
産後の体調不良は「しかたない」と諦めず、適切なケアを心がけましょう。
ママと赤ちゃんに与える影響
産後の鉄分不足は体調不良だけでなく、免疫力の低下にもつながります。



傷や子宮の回復にも鉄分が必要なため、不足すると回復が遅れる可能性があるので注意が必要です。
精神面では鉄分不足によってセロトニンやドーパミンが低下すると、産後うつのリスクが高まることも分かっています。
イライラや不安感が増し、赤ちゃんとの愛着形成にも影響が出てしまうかもしれません。
また、赤ちゃんへの直接的な影響は少ないと考えられていますが、ママの体調不良によって十分な授乳が難しくなる可能性があります。
赤ちゃんの健やかな成長のためにも、ママの鉄分補給は重要なのです。
特に鉄分が足りなくなるのはいつ?


産後に鉄分が不足しやすい時期と、それぞれの対策について見ていきましょう。
帝王切開・多量出血時
帝王切開は手術のため、通常の出産方法よりも多くの血液を失います。
また、多量出血があった場合は貧血症状がより顕著に現れやすく、回復にも時間がかかります。
出血量が多いと頭痛やふらつき、だるさといった体調変化が出やすいため注意が必要です。



帝王切開後や多量出血があった場合は、医師の指示に従って積極的な鉄分補給をおこないましょう。
出血が多い場合は医療機関での鉄剤投与や、輸血が必要になる可能性があります。
回復には個人差があるため、無理せず医師と相談しながら適切な鉄分補給を進めていきましょう。
出産直後から数週間
出産直後から数週間は特に鉄分が不足しやすい時期です。
出産による出血で大量の血液を失うため、体内の鉄分が一気に減少します。
産褥期と呼ばれるこの時期は、悪露(おろ)の排出も続いており、少量ながらも出血が続きます。
さらに、傷や子宮の回復にも鉄分が使われるため、消費が激しいのです。
また、睡眠不足や育児の疲れも重なり、食事が不規則になりがちなことも鉄分不足を悪化させる要因です。
特にこの時期は、意識して鉄分を摂取する必要があるため、鉄分豊富な食事を心がけましょう。



無理をせず、周囲のサポートを得ながら十分な休息を取ることも大切です。
授乳期・月経再開時
授乳が軌道に乗る産後1〜3ヶ月頃と、月経が再開する時期にも注意が必要です。
授乳中は母乳を作るために鉄分が使われるため、鉄分が減りやすくなります。



また、産後4〜6ヶ月頃から月経が再開すると、出血によってさらに鉄分が失われます。
特に最初の月経は出血量が多くなる傾向があり、一度に多くの鉄分が減ることも。
この時期は産後の回復が進んだと感じやすいですが、まだまだケアが必要な時期です。
日頃から鉄分が豊富な食品を摂るように心がけ、体調の変化を感じたら早めに対処しましょう。
必要に応じて医師に相談し、鉄剤の使用も検討することが大切です。
産後の鉄分補給のポイント


- ヘム鉄と非ヘム鉄をバランス良く摂取する
- ビタミンCやクエン酸と合わせて摂る
- 鉄分吸収を妨げるものを控える
- 少量ずつ複数回に分けて摂る



鉄分には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類があります。
| ヘム鉄 | 肉や魚などの 動物性食品に含まれる | 吸収率が約15〜20% |
|---|---|---|
| 非ヘム鉄 | 植物性食品に含まれる | 吸収率が2〜5% |
どちらもバランスをよく取り入れることが大切です。
また、鉄分の吸収を良くするためには、ビタミンCやクエン酸を一緒に摂るのがおすすめです。
反対に、お茶やコーヒーに含まれるタンニンは鉄分の吸収を妨げるため、鉄分を含む食事の30分前後は控えましょう。
鉄分は一度にたくさん摂るより朝昼晩と少しずつ分けて摂る方が効果的です。
毎日の食事で鉄分を意識し、間食にも鉄分が豊富な食品を取り入れてみてください。
参考:埼玉医科大学「鉄分の多い食品とビタミンCは一緒に考えましょう」
鉄分が豊富で摂りやすい食べ物


日常的に取り入れやすく、調理も簡単なものをご紹介します。



効率よく鉄分を補給するために、参考にしてみてください。
以下、鉄分の豊富な食べ物の一覧です。多い順に並べています。
鉄分の豊富な食べ物一覧
| 順位 | 食品名 | 100gあたりの鉄分量(mg) |
| 1 | あおのり(素干し) | 77.0 |
| 2 | 岩のり(素干し) | 48.0 |
| 3 | 乾燥きくらげ | 35.0 |
| 4 | あさりの缶詰(水煮) | 30.0 |
| 5 | せん茶 | 20.0 |
| 5 | 豚スモークレバー | 20.0 |
| 6 | かたくちいわし(煮干し) | 18.0 |
| 7 | しじみ(水煮) | 15.0 |
| 8 | 純ココア | 14.0 |
| 9 | 豚レバー | 13.0 |
| 10 | はぜのつくだ煮 | 12.0 |
| 11 | 焼きのり | 11.0 |
| 12 | 鶏レバー | 9.0 |
| 12 | 砂肝 | 9.0 |
| 12 | 乾燥大豆(黄大豆、全粒) | 9.0 |
| 13 | しじみ | 8.3 |
| 14 | 全粒きな粉 | 8 |
| 15 | 豚レバーペースト | 7.7 |
| 16 | パセリ(葉/生) | 7.5 |
| 16 | 凍り豆腐 | 7.5 |
| 17 | 牛ビーフジャーキー | 6.4 |
| 18 | 脱皮きな粉 | 6.2 |
| 19 | 牛レバー | 4.0 |
| 20 | あさり | 3.8 |
| 20 | 和牛肉(もも/焼き/皮下脂肪なし) | 3.8 |
| 21 | がんもどき | 3.6 |
| 22 | コンビーフ | 3.5 |
| 23 | 切り干し大根 | 3.1 |
| 23 | 葉大根 | 3.1 |
| 24 | 小松菜(葉/生) | 2.8 |
| 24 | 和牛肉 | 2.8 |
出典:「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
この表は日本食品標準成分表2020年版(八訂)を参考に作成しています。実際の含有量は商品や調理法によって異なる場合があります。
あさりの缶詰(水煮)
あさりの缶詰は100gあたり約30mgの鉄分を含みます。
保存がきいて調理も簡単なので、忙しいママにぴったりです。



缶詰の汁にも鉄分が溶け出しているため、汁ごと料理に活用するのがおすすめです。
パスタやスープの具材にしたり、味噌汁に入れるだけでも手軽に鉄分を補給できます。
和風パスタや炊き込みご飯、簡単なアヒージョなどアレンジも豊富です。
また、あさりには鉄分の吸収を助けるビタミンB12も含まれているため、効率的に鉄分を摂取できます。
料理が苦手なママでも手軽に取り入れられる食材です。
かたくちいわし(煮干し)
かたくちいわしは小さな体に驚くほどの鉄分を含んでいます。
100gあたり約18.0mgの鉄分を含み、カルシウムやビタミンDも豊富です。
丸ごと食べられるため、効率的に栄養を摂取できるのが魅力です。



おやつとしてはもちろん、味噌汁のだしや粉末にしてふりかけにするなど、さまざまな活用法があります。
常温保存もできるため、いつでも手軽に取り入れられる優秀な鉄分です。
小松菜
小松菜は植物性食品の中でも特に鉄分が豊富な野菜です。
100gあたり約2.8mgの鉄分を含み、鉄分の吸収を妨げるシュウ酸がほうれん草より少ないのが特徴です。
さらに、鉄分の吸収を高めるビタミンCも豊富に含んでいます。
サッと茹でて和え物にしたり、炒め物や汁物の具材にしたりと調理法も豊富です。
スムージーに加えれば、朝の忙しい時間にも手軽に栄養補給できます。



レモン汁などをかけると、ビタミンCの効果で鉄分の吸収がより期待できます。
小松菜には葉酸やカルシウムも含まれるため、日々の健康維持にも役立つでしょう。
焼きのり
焼きのりは意外な鉄分として注目されています。
焼きのり100gあたり約11.0mg、全形1枚(約3g)で約0.9mgの鉄分を含み、手軽に取り入れやすいのが魅力です。
おにぎりはもちろん、味噌汁や納豆に加えたり、サラダに混ぜたりするのもおすすめです。



のりの風味が料理のアクセントになり、美味しく鉄分補給ができます。
また、焼きのりは食物繊維やビタミンB12も豊富です。
常温で長期保存できるため、ストックしておくと忙しい産後ママの強い味方になるでしょう。
乾燥剤と一緒に密閉容器で保管すると、パリパリの食感を保てます。
きな粉
きな粉は大豆を炒って粉にした食品で、鉄分やたんぱく質が豊富に含まれています。
100gあたり約6.2〜8.0mgの鉄分が含まれており、植物性食品の中でも鉄分が多いのが特徴です。
ビタミンやカルシウム、食物繊維も含まれており、腸内環境を整える働きも期待できます。



きな粉に含まれる鉄分は「非ヘム鉄」で吸収率がやや低めですが、ビタミンCと一緒に摂れば吸収率が高まります。
ヨーグルトに混ぜたり、スムージーに加えれば、無理なく続けられますね。
ただし、過剰摂取はイソフラボンの上限目安量を超える可能性があるため、他の大豆製品の摂取量も考慮しましょう。
きな粉を上手に活用して、必要な鉄分を補い、体のコンディションを整えましょう。
しじみの缶詰(水煮)
しじみは肝臓に優しい食材として知られていますが、実は優れた鉄分でもあります。
しじみの缶詰は100gあたり約15.0mgの鉄分を含みます。
缶詰なので長期保存が可能で、調理も簡単です。



味噌汁の具材として使うのが定番ですが、炊き込みご飯やパスタソースなど、さまざまな料理に活用できます。
また、しじみに含まれるオルニチンは肝機能をサポートし、産後の回復にも役立つと言われています。
さらに、鉄分の吸収を助けるビタミンB12が豊富に含まれている優秀な食べ物です。
缶詰の汁にも栄養が溶け出ているため、汁ごと利用するのがおすすめです。
鉄分の吸収を高める栄養素


鉄分を効率よく体内に取り入れるには、吸収を助ける栄養素の摂取が欠かせません。
以下では、鉄分の吸収を高める栄養素について解説します。
ビタミンC
ビタミンCは鉄分の吸収を助ける大切な栄養素です。
特に植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」は体に吸収されにくい性質がありますが、ビタミンCと一緒に摂れば吸収率が高まります。
ビタミンCが豊富な食べ物には、レモンやオレンジなどの柑橘類、キウイ、イチゴ、パプリカ、ブロッコリーなどが挙げられます。



小松菜のお浸しにレモン汁をかけたり、豆腐料理にパプリカを加えると手軽に摂取できますね。
ただし、ビタミンCは熱に弱い性質を持つため、生で食べるか、加熱する場合は短時間で調理しましょう。
また、野菜や果物は新鮮なものを選ぶとより多くのビタミンCがとれます。
日々の食事にビタミンCを取り入れ、効率的な鉄分補給を心がけましょう。
葉酸
葉酸は鉄分の代謝や、赤血球の生成に関わる重要な栄養素です。
鉄分と一緒に摂取すると、体内での鉄の利用がスムーズになり、貧血予防にも役立ちます。
葉酸は母乳の生成や体の回復もサポートしてくれるため、産後や授乳期も欠かせません。
葉酸が豊富な食品には、ほうれん草や小松菜などの緑黄色野菜、枝豆、アボカド、納豆などがあります。



特に緑の濃い葉物野菜は葉酸と鉄分の両方を含むため、一石二鳥の食材といえるでしょう。
葉酸もビタミンCと同様に熱に弱いため、調理の際は短時間で仕上げるのがコツです。
また、葉酸は水に溶けやすい性質があるため、茹でる場合は茹で汁も無駄にせず、スープなどに活用するとより効率的です。
産後は特に葉酸の需要が高まる時期なので、意識して摂取しましょう。
クエン酸
クエン酸には、鉄分を水に溶けやすくする働きがあります。
この性質により、腸での吸収がスムーズになると考えられています。



特に、植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」は体に吸収されにくいため、クエン酸やビタミンCと一緒に摂るのがおすすめです。
梅干しやレモンなどを食事の際に意識して取り入れてみましょう。
鉄分補給を意識する際は、量だけでなく吸収のしやすさにも目を向けてみてください。
頑張りすぎず、サプリも上手に使おう


産後は忙しく、食事では十分な量の鉄分が摂れない時もあります。
そんな時は、サプリメントを活用するのも一つの方法です。



鉄分サプリメントには「ヘム鉄タイプ」と「非ヘム鉄タイプ」があります。
ヘム鉄は吸収されやすく、胃への負担が少ないとされています。
非ヘム鉄は価格が手ごろですが、人によっては胃の不調を感じる場合もあるため、自分に合うタイプを選ぶことが大切です。
サプリメントを選ぶ際は、鉄分だけでなく、ビタミンCや葉酸など鉄分の吸収を助ける栄養素が含まれているものを選びましょう。
また、授乳中でも安心して摂取できるかどうかも確認しましょう。
「完璧な食事」にこだわりすぎず、サプリメントも上手に活用して、無理なく鉄分補給を続けることが大切です。
ただし、サプリメントはあくまで食事のサポートです。
医師や薬剤師に相談しながら、適切な量を守って摂取しましょう。
さらにプラス!鉄分補給方法


鉄分の吸収を良くするには、食事のタイミングを意識しましょう。
お茶やコーヒーに含まれるタンニンは、鉄分の吸収を妨げます。



そのため、鉄分を含む食事の30分前後は控えると安心です。
代わりにビタミンCを含むオレンジジュースなどを飲むと鉄分の吸収が高まります。
さらに、鉄製の調理器具を使うと、自然に料理に鉄分が加わるのでおすすめです。
特に酸味のある料理(トマト系やレモン汁を使ったもの)は鉄分が溶け出しやすくなると言われています。
また、適度な運動も鉄分の代謝を助けます。
赤ちゃんとのお散歩など、無理のない範囲で体を動かすことを心がけましょう。
ただし、激しい運動は逆効果になる場合があるため、産後の回復状況に合わせて様子を見ながら進めましょう。
産後の鉄分不足に関するQ&A
産後の鉄分不足に関するよくある質問をまとめました。
まとめ





産後ママは出産時の出血や授乳によって鉄分不足になりやすく、疲労感やめまい、集中力低下などの不調が現れることがあります。
鉄分は子宮の回復や免疫力維持にも不可欠なため、意識的な補給が大切です。
- ヘム鉄(動物性)と非ヘム鉄(植物性)をバランスよく摂取
- あさりやしじみの缶詰、煮干しや小松菜、焼きのりやきな粉などを活用
- ビタミンC・葉酸・クエン酸と一緒に摂るとさらに効果的
無理せず食事とサプリメントを上手に組み合わせて、産後の体調管理に役立てましょう。
