この記事で解決できるお悩み
- 産後はどんな栄養素が必要なの?
- 控えた方がいい食べ物はあるの?
- おすすめの食べ方は?
 Yuri
Yuriこの記事で紹介する「7つの栄養素と、おすすめの食べ方4つ」を実践すれば、健康的な食事管理ができます。
記事前半では産後に必要な栄養素について、後半では控えたい食品を解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。
この記事を読んで、無理なく産後の体をリカバリーしましょう。
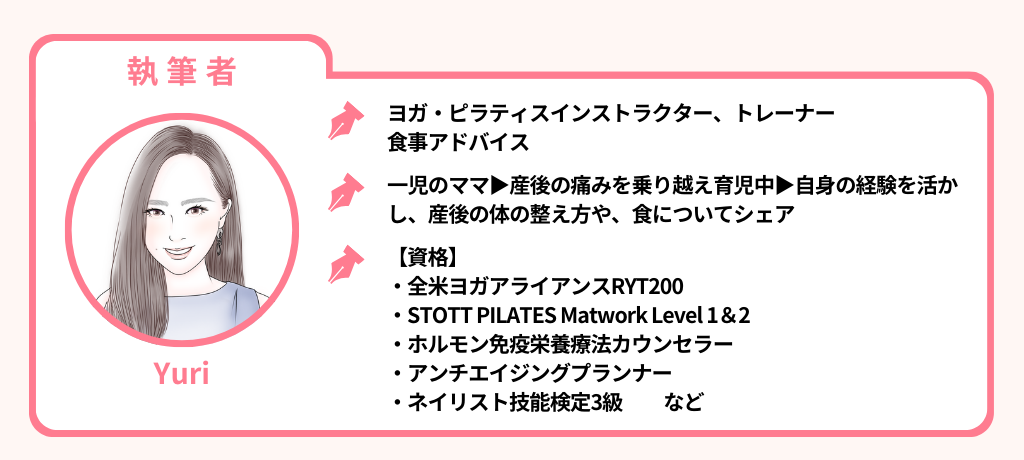
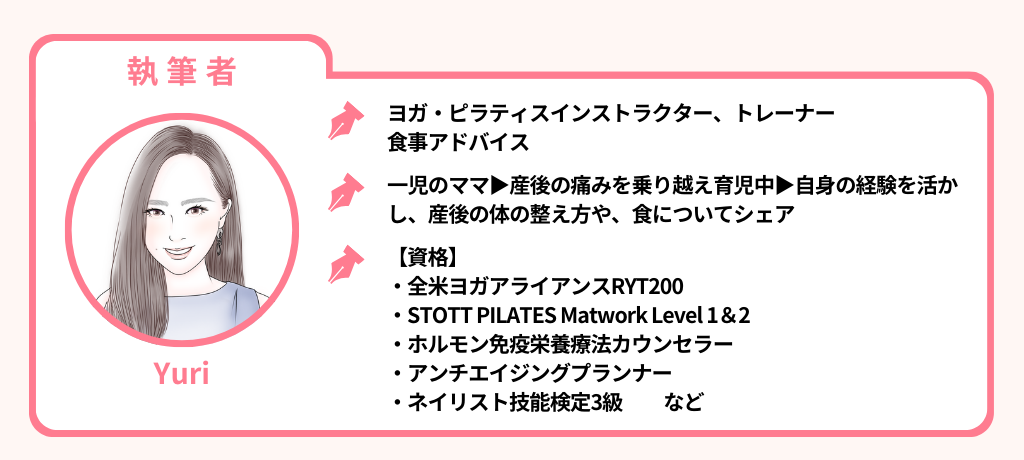
産後の栄養不足がもたらす影響とは?


産後の女性は普段より多くの栄養を必要としますが、「育児に追われて十分な食事が取れない」という声が多いのが現状です。



産後の栄養不足は体の回復を遅らせるだけでなく、赤ちゃんの健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
また、栄養素が不足すると骨密度の低下や貧血、疲労感の増大とさまざまな不調を感じやすくなる恐れがあります。
母乳の質にも影響を与えるため、赤ちゃんの成長に影響が出る可能性もあるのです。
十分な栄養摂取は産後の回復を促進し、母子ともに健康な生活を送るための土台となります。
そのため、産後は食事内容に気を配ることが大切です。
産後に摂りたい7つの栄養素


産後の女性が積極的に摂りたい栄養素を紹介します。
順番に解説していきます。
たんぱく質
筋肉の回復、母乳の生成に不可欠
(魚、卵、豆類など)
たんぱく質は産後の体力回復と、母乳の質の向上に不可欠な栄養素です。
出産で弱った筋肉や組織の修復を助け、母乳の主要成分としても重要な役割を果たします。



おすすめの食材は魚や卵、大豆製品です。
特に魚はたんぱく質だけでなく、DHAやEPAも豊富に含まれているため一石二鳥です。
また、豆腐や納豆などの大豆製品は植物性たんぱく質で、胃腸への負担も少ないため積極的に摂りましょう。
1日の摂取目安量は体重1kgあたり約1.1gですが、授乳中はさらに多く必要です。
毎食たんぱく質を含む食品を取り入れると、効率的に摂取できるでしょう。
カルシウム
骨の健康維持、母乳のカルシウム源
(小魚、緑黄色野菜など)
カルシウムは丈夫な骨を保ち、栄養たっぷりの母乳を作るために欠かせない栄養素です。
カルシウムが不足すると、骨がもろくなる骨粗鬆症(こつそしょうしょう)になるリスクが高まります。
産後は骨からカルシウムが溶け出しやすくなるため、普段以上に必要です。
1日のカルシウム摂取目安量は約650mgですが、授乳中はさらに多く必要です。
カルシウムを多く含む食材としては小魚や緑黄色野菜が挙げられます。
煮干しやいわしなどの小魚を丸ごと食べると、効率的にカルシウムを摂取できるでしょう。
緑黄色野菜では小松菜やブロッコリーなどがおすすめです。



また、カルシウムはビタミンDと一緒に摂ると、より吸収されやすくなります。
ビタミンDは日光を浴びることで体内で作られます。そのため、赤ちゃんと積極的に散歩をしましょう。
鉄分
貧血予防、母乳の質の向上
(レバー、赤身肉、海藻類など)
鉄分は産後の貧血予防に特に重要な栄養素です。
出産時の出血により失われた鉄分を補充し、赤血球の生成や酸素運搬を助ける役割を果たします。
鉄分を多く含む食材としてはレバーやひじき、小松菜などが挙げられます。



植物性の鉄分は吸収率が低いため、ビタミンCと一緒に摂取し吸収率を高めましょう。
小松菜のお浸しにレモン汁をかけたり、ひじきの煮物にみかんを添えたりするのがおすすめです。
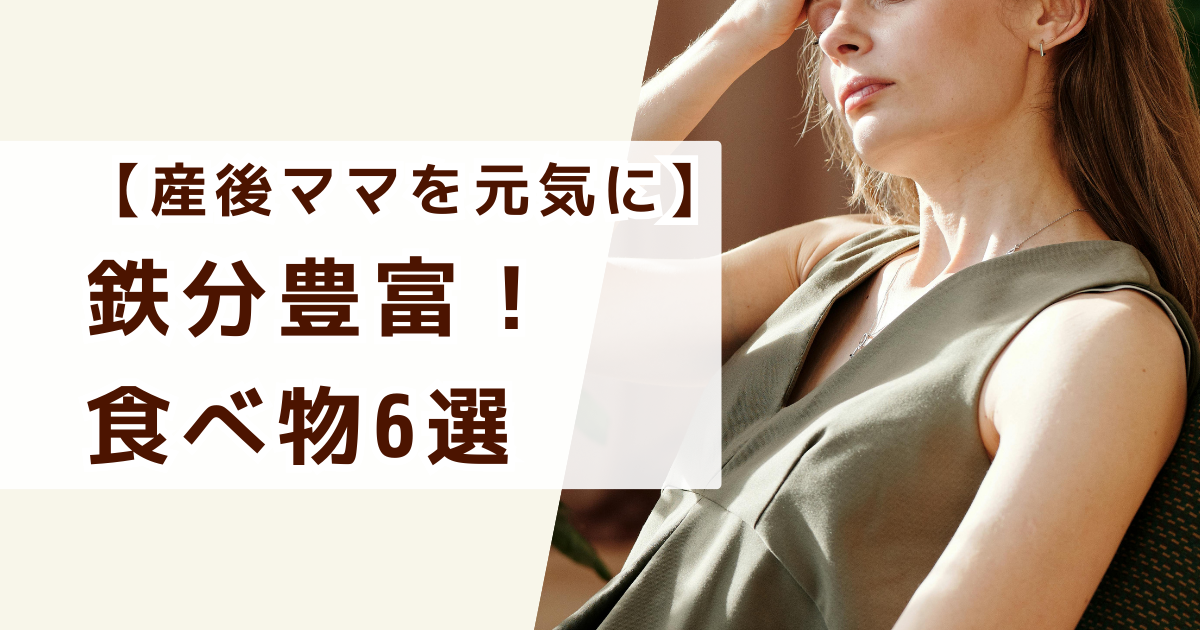
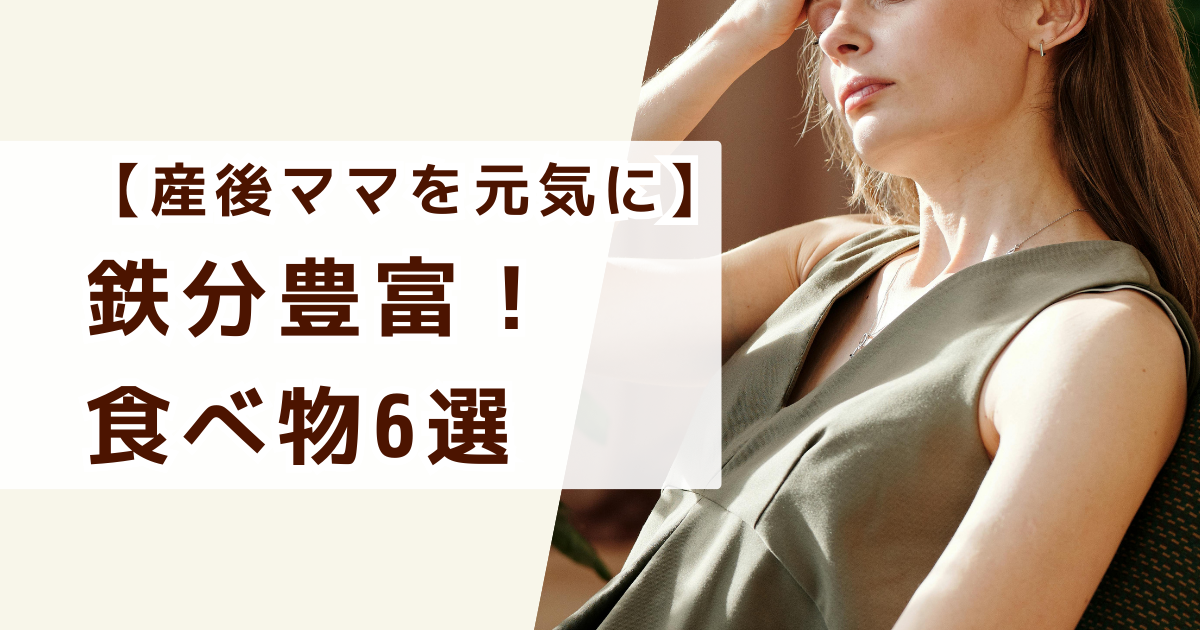
葉酸
赤血球の生成を促す
(緑黄色野菜、豆類、柑橘類など)
葉酸は赤血球の生成を助け、細胞の新陳代謝を促進する重要な栄養素です。
葉酸が不足すると、貧血や疲労感の増加、母乳の質の低下など問題が生じる可能性があります。
産後は体の回復と母乳生成のために、十分な葉酸摂取が必要です。



葉酸を多く含む食材としては緑黄色野菜や納豆、レバーなどが挙げられます。
特に緑黄色野菜は葉酸が豊富です。
また、納豆は発酵食品であるため、腸内環境の改善にも役立ちます。
葉酸は熱に弱い性質があるため、生で食べられる野菜はなるべく加熱せずに摂取するのが効果的です。
授乳中のママの摂取目安量は、1日340μg(マイクログラム)ですが、個人の状態に応じて調整が必要な場合もあります。
摂取量が気になる場合は医師や栄養士に相談してみましょう。
ビタミンC
疲労回復や免疫力を高め、鉄分の吸収を促進
(柑橘類、パプリカなど)
ビタミンCは疲労回復や免疫力を高める働きがある栄養素です。
鉄分の吸収を助ける働きもあるため、産後の貧血予防にも役立ちます。
さらに、ビタミンCは抗酸化作用があるため、肌の健康維持にも寄与します。
ビタミンCを多く含む食品は、柑橘類や緑黄色野菜です。



特にレモンやグレープフルーツ、キウイフルーツなどの果物は手軽にビタミンCを摂取できる食材です。
また、ブロッコリーやパプリカなどの野菜にも豊富にビタミンCが含まれています。
ビタミンCは熱や光に弱いため、生で食べるか、さっと調理するのがおすすめです。
授乳中のママは1日に120mgのビタミンC摂取が推奨されていますが、ストレスが多いときは、さらに多く摂る必要があります。
育児で忙しい時だからこそ、しっかりビタミンCを補給し、健康な肌と免疫機能を維持しましょう。
DHA・EPA
抗炎症作用、赤ちゃんの脳の発達や認知機能に寄与
(青魚、オメガ3の油など)
授乳中のママに欠かせないのが、DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)です。



これらの栄養素は赤ちゃんの脳や認知機能に重要で、ママの健康維持にも役立ちます。
DHA・EPAを多く含む食材は青魚で、サバやイワシなどを週2〜3回食べるのがおすすめです。
魚以外では、オメガ3の油にDHA・EPAが多く含まれています。
オメガ3の油は酸化しやすいので、サラダにかけたりして生のまま摂取しましょう。
また、DHA・EPAのサプリメントを利用するのも一つの方法です。
ただし、その場合は医師や栄養士に相談してから摂取をしましょう。
1日のDHA・EPA摂取量は明確に定められていませんが、青魚を週に約90g程度食べることが推奨されています。
母乳を介して赤ちゃんに届けられるため、授乳期間中は特に意識して摂りましょう。
十分な水分
代謝を促進
(水、白湯など)
水分は代謝を促してくれるため、母乳の生成に欠かせません。



水分不足は便秘や尿路感染症のリスクを高め、母乳の量にも影響を与える可能性があります。
特に産後は脱水になりやすいため、こまめな水分補給が必要です。
1日約2リットルを目安に水分を摂取しましょう。授乳中のママの場合は通常より500ml多い約2.5リットルが目安です。
産後の適切な栄養摂取は母体の回復と、赤ちゃんの健やかな成長を支える礎となります。
ママと赤ちゃんの健康のために、栄養バランスの取れた食生活を心がけましょう。
産後に控えたい食品や飲み物6つ


産後の食事はママと赤ちゃんの健康に直接影響を与えます。
特に母乳育児の場合は母乳を通じて赤ちゃんに栄養が届くため、配慮が必要です。
ミルク育児の場合は赤ちゃんへの影響は少ないものの、ママ自身の健康管理は大切です。
順番に解説していきます。
脂質や糖分が多い食品
脂質や糖分が多い食品は産後の回復を遅らせる恐れがあるため、控えるのが望ましいです。
これらの食品は血液を濃くし、乳腺炎のリスクを高める可能性があります。



また、過剰な摂取は体重増加につながり、産後の体型の戻りを遅らせる原因となります。
特に気をつけたい食品は揚げ物やケーキ、菓子パンやアイスクリームなどです。
完全に避ける必要はありませんが、摂取頻度や量を意識的に減らしましょう。
代わりに、良質な脂質を含む魚やナッツ類、自然な甘みのある果物などがおすすめです。
カフェインやアルコール
カフェインやアルコールは、母乳を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性があるため注意が必要です。



カフェインは赤ちゃんの睡眠パターンを乱したり、興奮させてしまうリスクがあります。
コーヒーや紅茶、緑茶やチョコレートなどに含まれているため、摂取量の管理が必要です。
カフェイン摂取量は、1日200~300mg以下(コーヒー約2杯分)に抑えましょう。
また、アルコールは母乳に移行し赤ちゃんの発達に悪影響を与える可能性があるため、授乳中は避けてください。
代わりに、水や白湯、ハーブティーなどを選び十分な水分補給を心がけましょう。
塩分が多い食品
塩分の取りすぎはむくみや高血圧のリスクを高めるため、産後は控えめにしましょう。



過剰な塩分摂取は体内の水分バランスを崩し、むくみを悪化させる可能性があります。
また、高血圧は母体の健康に悪影響を与えるため、母乳の質にも影響が出るかもしれません。
特に気をつけたい食品は漬物や塩蔵品、ハム・ソーセージなどの加工肉、インスタント食品などです。
1日の塩分摂取量は6g未満が目安です。
調理の際は塩の代わりにお酢やレモン汁などで風味を出すと、塩分を控えめにできます。
インスタント食品
インスタント食品は栄養バランスが偏りやすく、添加物も多いため産後は控えたい食品です。
これらの食品は塩分や糖分、脂質が多く含まれている一方で、ビタミンやミネラル、食物繊維が不足しがちです。



また、保存料や化学調味料などの添加物が多用されているケースも多く、母体や赤ちゃんの健康に影響を与える可能性があります。
特に気をつけたい食品はカップラーメンやレトルトカレー、冷凍ピザなどです。
これらの食品はできるだけ控え、新鮮な食材を使用した料理や添加物の少ない食事を心がけましょう。
時間がない場合は冷凍野菜や缶詰など、栄養価の高い加工食品を活用するのも一つの方法です。
また、週末にまとめて調理し小分けに保存しておくと手軽に食べられて便利です。
体を冷やす食べ物
産後は体を温めることが大切です。そのため、体を冷やす食べ物は控えめにしましょう。
体が冷えると血行が悪くなり、母乳の分泌に影響を与えたり、産後の回復が遅れたりする可能性があります。
特に気をつけたいのは、冷たい食べ物や飲み物、夏野菜などです。
冷蔵庫から出してすぐの冷たい食べ物や飲み物はできるだけ控え、常温に戻してから食べましょう。
温かいスープや煮物、蒸し野菜など、体を温める食べ物を積極的に取り入れるのもおすすめです。



特に寒い季節は体が冷えやすいので、食事の温度にも気を配り、内側から体を守って健康的に冬を乗り越えましょう。
生もの
産後は免疫力が低下しているため、慎重に生ものを摂取する必要があります。
しかし、妊娠中ほど厳しい制限は必要ありません。



授乳中のママが生ものを食べても、基本的には赤ちゃんに影響を与える可能性は低いとされています。
ただし、食中毒のリスクはあるので、以下の点に注意しましょう。
- 鮮度の良い食材を選ぶ
→ 新鮮な魚介類や野菜を使用し、適切な保存方法を守りましょう。 - 信頼できる店で購入する
→ 衛生管理の行き届いた店で購入しましょう。 - 適度な量と頻度を守る
→ 生ものの摂取は週1〜2回程度に抑えましょう。 - 体調に合わせて判断する
→ 体調不良時や疲労時は生ものを避け、加熱調理した食品を選びましょう。
産後の食事はママの体の回復と赤ちゃんの健康を支える重要な要素です。
バランスの取れた食事を心がけ、ママと赤ちゃんの健康を守りましょう。
おすすめの食べ方4つ


日々の食事を少し工夫するだけで、ママと赤ちゃんの健康づくりにつながります。
以下に、無理なく続けられるおすすめの食べ方4つをまとめました。
それぞれ解説していきます。
一汁三菜を意識する
一汁三菜は日本の伝統的な食事スタイルで、産後の食事にも適しています。
この食事構成は、主食(ご飯)、汁物(味噌汁など)、主菜(魚や肉のおかず)、副菜(野菜のおかず)2品から成り立ちます。
この組み合わせにより、バランスの取れた栄養摂取が可能になるのです。
産後の一汁三菜の具体例
- 主食:玄米ご飯(食物繊維とビタミンB群が豊富)
- 汁物:小松菜と油揚げの味噌汁(カルシウムと鉄分を補給)
- 主菜:鮭の塩焼き(良質なたんぱく質とDHAを摂取)
- 副菜1:ほうれん草のお浸し(鉄分と葉酸を補給)
- 副菜2:切り干し大根の煮物(食物繊維とカルシウムを摂取)
このように、一汁三菜を意識すると、産後に必要な栄養素をバランスよく摂取できます。



ただし、毎食用意するのは大変なので、無理のない範囲で取り入れていきましょう。
時間がないときは、冷凍野菜や作り置きのおかずを活用するなど、工夫して栄養バランスを整えましょう。
食材の栄養価を意識する
産後の食事では特に栄養価を意識する必要があります。
各食材に含まれる栄養素を理解し食材を組み合わせると、効果的に栄養が摂取できます。
例えば、鉄分とビタミンCを多く含む食材を一緒に食べると、鉄分の吸収率が高まります。



また、調理方法によっても栄養価が変わります。
例えば、水溶性ビタミン(ビタミンB群・ビタミンCなど)は煮物より蒸し物や炒め物の方が、損失が少なくなるためおすすめです。
一方で、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・Kなど)は、油と一緒に調理すると吸収率が高まります。
食材の栄養価や組み合わせ、調理法を意識することで、より効果的な栄養摂取が可能になります。
よく噛んで食べる
一口30回を目安によく噛んで食べましょう。
「よく噛んで食べること」には、以下のメリットがあります。
- 消化吸収の促進
→ 必要な栄養素をより効率的に体内に取り込めます。 - 満腹感の獲得
→ 脳が満腹感を感じやすくなります。 - だ液の分泌促進
→ だ液の分泌が促進されます。だ液には消化を助ける酵素が含まれているため、口腔内を清潔に保つのにも役立ちます。 - あごの筋肉の強化
→ あごの筋肉が鍛えられます。これは顔のたるみ予防にも効果的です。
産後は忙しく、ついつい急いで食事を済ませてしまいますが、できるだけよく噛みましょう。



栄養吸収が良くなり、産後の回復や母乳の質の向上にもつながります。
こまめに水分を摂る
十分な水分摂取は、産後の女性にとって大切です。
特に授乳中は母乳の生成に多くの水分が使われるので、意識的に補給しましょう。
適切な水分摂取には、以下のようなメリットがあります。
- 母乳の生成促進
→ 母乳の量を維持し、質を向上させるのに役立ちます。 - 便秘の予防
→ 腸の動きを促進し、産後によく見られる便秘予防にも効果的です。 - 疲労回復
→ 体内の代謝を促進し、疲労回復を助けます。 - 肌の健康維持
→ 肌の乾燥を防ぎ、産後の肌トラブルの予防に役立ちます。
一度に大量に飲むのではなく、少しずつこまめに飲むのがコツです。



水や白湯などがおすすめですが、過剰摂取には注意をしましょう。
水分摂取を習慣化すると、産後の健康管理がより効果的になりますよ。
産後の食事に関するQ&A
産後の食事に関するよくある質問をまとめました。
まとめ


産後ママは妊娠中よりも多くの栄養を必要としますが、育児に追われて食事が疎かになりがちです。



栄養不足はママの体の回復を遅らせるだけでなく、母乳の質にも影響を与えるため、意識的な食事管理が大切です。
おすすめの食べ方は一汁三菜を意識する、食材の栄養価を考える、よく噛んで食べる、水分をこまめに摂るなどが挙げられます。
産後の体調回復と母乳の質の向上のために、栄養バランスを考えた食事を心がけましょう。
